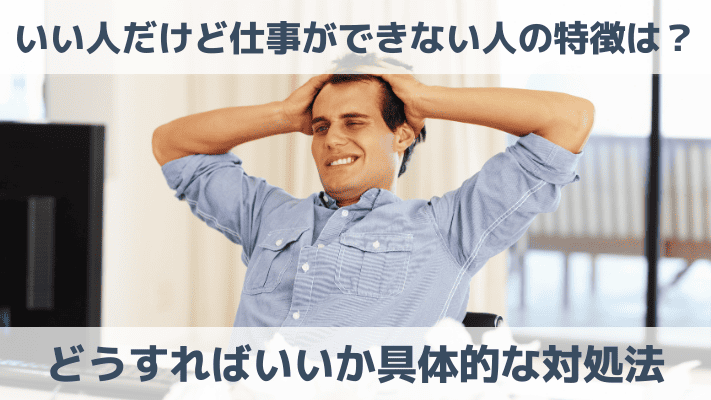いい人だけど仕事ができない人の特徴は、人当たりは良いが業務の遂行が遅い、誠実さはあるものの決断力に欠ける、協調性は高いが責任感が薄い、他人の意見に流されやすい、時間管理が苦手で期限を守れないことがあげられます。具体的な対処法は、目標設定と期限の明確化、フィードバックの積極的な実施、コーチングによる意識の改革です。

いい人だけど仕事ができない?
職場で「いい人」はたくさんいますが、仕事ができる「いい人」とできない「いい人」がいるのも、また事実。
後者にはどんな特徴があるでしょうか。
コミュニケーション能力が高く、友人にも優しいけれど、なぜか仕事に関してはいつも一歩遅れがち。
どうして彼らはスムーズに業務を遂行できないのでしょうか。
誠実さは人一倍なのに決断が遅い。協調性があるけど責任感がない。…そんな彼らの日常に効果的な対処法で変わるかもしれません。
この記事では、「いい人だけど仕事ができない人」のあるある特徴とその解決策を掘り下げて解説していきます。
目標設定から時間管理、そして組織的な支援まで、一人ひとりが能力を発揮できるためのヒントを提供します。
仕事もプライベートも充実させたいあなた、具体的な改善策を探ってみませんか。
いい人だけど仕事ができない人の特徴
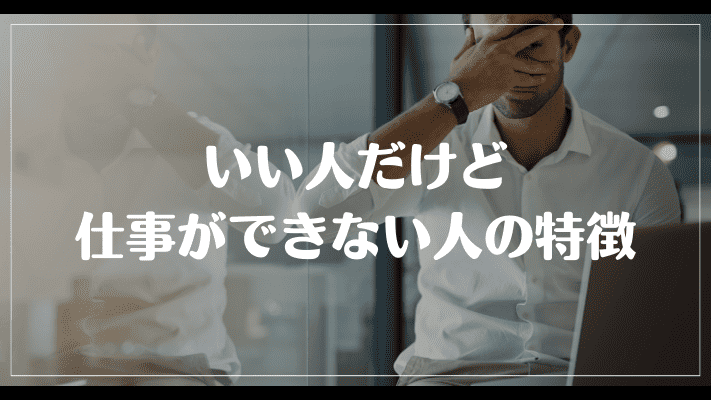
業務と人間関係は相反することがしばしばあります。純粋な人柄や人間関係への配慮は職場に必要不可欠ですが、成果が望まれる昨今の職場環境ではこうした資質のみでは、求められるパフォーマンスに達しないことも少ないはありません。
ここでは、人格は素晴らしいのだけれど、仕事の成果を出す上で苦労する人の特徴を掘り下げていきましょう。
人当たりは良いが業務の遂行が遅い
円滑なコミュニケーション能力は人間関係構築に欠かせません。
しかし、話が弾む一方で、業務への集中が切れてしまうことがあります。
その結果、タスクの遂行に時間がかかり、業務の効率が落ちてしまうことも。
例えば、楽しい会話を優先しその場の雰囲気を大切にするあまり、自分の仕事に戻るタイミングを見失うといった状況です。
また、問題が生じた際に間に立って解決しようとする姿勢は評価されるものの、それにより自分の仕事が滞る状況も見受けられます。
誠実さはあるものの決断力に欠ける
誠実な人は周囲からの信頼が厚く、細部まで気を配ることができます。
しかし、時として決断を下すことに難渋してしまうことも。
何を優先すべきか慎重に考える余り、迅速な判断が求められる状況で十分な速度で決断が出来ないことがあります。

臨機応変な対応が必要とされるビジネスシーンでは、
このような特性が逆に足枷になることが少なくありません。
誠実さとは裏腹に、肝心のタイミングでの迅速なアクションが取れず成果を出すことが難しくなるわけです。
協調性は高いが責任感が薄い
対人関係を大切にすることはチームワークの向上に寄与しますが、友達思いが過ぎると仕事の責任感が希薄になるリスクがあります。
他人を気遣い支える姿勢は素晴らしいのですが、自らの業務において最終的な成果を出すという自覚が薄れることも。
仲間との良好な関係を保ちたいがためにはっきりと「いいえ」と言えないので、結果として自分の業務に充分な時間を割けず、品質の低下を招くことが考えられます。
積極性に乏しい
積極性が足りない人は待ちの姿勢が目立ちます。
指示を仰がず自ら前に出て行動するのが苦手なため、仕事を進める上での自立性が低いとされることがあります。
自分自身で業務を見つけ、推進する能力が問われる現代のビジネスシーンでは、積極的にチャレンジする姿勢が求められます。
しかし、この特性を持つ人は自発的に動くのを躊躇し、結果としてプロジェクトやタスクが滞ってしまうことがあるのです。
人間関係を重視し業務がおろそか
良好な人間関係を築く力は、職場の雰囲気を良くし、心地よい職場環境を作り出します。
しかし、人間関係を優先し過ぎると、業務の進行をおろそかにしてしまう可能性があります。
- 同僚の話に同情し、そのトラブル処理を手伝ううちに、自分の業務が後回しにされる
- 不快な感情を避けようと、難しい話題や厳しいフィードバックを避けることで、仕事の進捗や問題解決に必要なコミュニケーションが取れない場合も
他人の意見に流されやすい
他人の意見を尊重することは円滑なコミュニケーションに必要ですが、あまりに流されやすいと自分の判断力が生かせず、自立した意思決定が難しくなります。
物事に対して自分の意見を持たず、決められたことに従ってしまう傾向があるため、業務を進める上で主導権を握ることができないのです。
その結果、時には自分に不利な判断を受け入れることになりかねず、職場での発言力やプロジェクトへの影響力を持てない状態に陥ることがあります。
時間管理が苦手で期限を守れない
効果的な時間管理は、仕事の成果を出す上で不可欠です。
時間管理が苦手な人は、終日を通しての業務の段取りがうまくいかず、結果として締切を過ぎてしまうことがあります。
この特性の人はプランニングに欠けがちで、日々のタスクや長期的な目標に対するスケジュール管理が不得手です。
締め切りを意識せずに過ごし、急な期限に追われてバタバタと作業することになるため、成果の質と量の低下が懸念されます。
いい人だけど仕事ができない人はどうすればいいか対処法
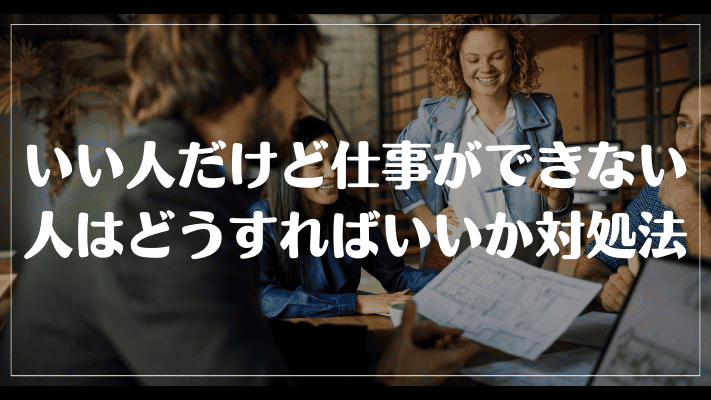

誠実でありながら仕事で結果が出せない人は一定数、存在します。
そういった人々が自身の能力を最大限に引き出し、業務成果をあげるためには、具体的かつ効果的な対処法が必要です。
効率的な時間管理、優先順位の設定、そしてフィードバックを通じて、仕事の質を改善していく方策を検討しましょう。
目標設定と期限の明確化
仕事ができない人が直面する問題は、目標の設定と期限の不明確さにあります。
目標をはっきりさせ、それを達成するための期限を設けることで、
仕事への取り組み方が具体的になり、計画を立てやすくなります。
これらの目標を小さく分けることで、達成が容易になり、モチベーションの維持もしやすくなるのです。
遅い遂行にはタイムマネジメントの指導
業務の遅延は、タイムマネジメントの不備に起因します。
従って、効果的な時間管理手法の習得が必要です。

課題毎に時間を割り当て、優先順位をつける練習から始めます。
また、プロジェクト管理ツールを使用することで、視覚的にタスクの進行状況を追跡し、時間監視の意識も高められます。
時間管理のスキルをマスターする方法
時間を上手に管理するためのスキルは習得が可能です。
まずは自分の時間が何に使われているかを把握し、無駄な活動を削減します。
- 一日の始まりに最も重要なタスクから取りかかる時間ブロッキング
- ポモドーロテクニック
また、計画通りに進まない場合の対応策も検討する必要があります。
優先順位の明確化とタスク管理の徹底
日々の業務を効率良く進めるためには、タスクに対する優先順位の設定が不可欠です。
それぞれのタスクの緊急度と重要度を考えることで、何に着手すべきか判断しやすくなります。
この明確化により、タスク管理が徹底され、期限内に質の高い成果を出しやすくなるのです。
意思決定のスキルアップ
決断力を養うことは、効果的な優先順位付けに直結します。
リスクと報酬を天秤にかけ、意思決定を迅速に行うためには、問題解決能力と判断力を高める練習が必要です。
ケーススタディを用いたトレーニングや、決断を下す際のフレームワークを学ぶことにより、無駄な迷いを減らし、自信を持って次の一手を打てるようになります。
業務重視の意識改革
忙しい毎日の中で、根本的な業務改革の必要性が見過ごされがちです。

時間をかけても成果が得られない場合、作業手順の見直しや、効率化のための技術導入を検討することが大切です。
定期的なレビューを通じて、業務プロセスのボトルネックを特定し、業務改善に努めます。
また、チームメンバーとのコミュニケーションを強化し、業務の透明性を高めることも、全員が目標に向かって進むための重要なステップです。
フィードバックの積極的な実施
フィードバックは個人の成長に欠かせない要素です。
定期的に自己評価を行い、他者からの意見を受け止めることによって、仕事の遂行能力が向上します。
特に目標に関するフィードバックは、目標設定の妥当性を検証し、必要に応じて修正を加えるために役立ちます。
定期的なフィードバックにより、自分自身に正直な自己評価と、建設的な他者の意見が成長を促進するのです。
責任感の向上策
業務における責任感を高めるためには、自分の行動がチームやプロジェクトに与える影響を意識することが必要です。
自身の役割を再認識し、タスクへの取り組みにおいて主体性を持つことで、質の高い結果へと繋がります。
コミットメントを明確にし、達成した際には適切な評価や報酬が得られるような仕組みを設けることも、責任感の向上に寄与します。
小さな成功を積み重ねる
仕事の能力を向上させるには、まず小さな成功から始めることが大切です。
小さな目標を設定し、それを達成することで自信を育てます。
また、成功体験を積み重ねることにより、より大きな課題に対する挑戦も怖れずに取り組むことができるようになります。
継続的な成長を目指して、毎日の業務において進展を記録し、共有し、祝福する文化をチーム内で育んでいきましょう。
定期的な自己評価と目標の見直し
成果を出すためには、自分自身の業務の進め方を定期的に振り返り、
自己評価を行うことが重要です。
この習慣は、自身の強みや弱みを認識し改善する上で役立ちます。
目標を定期的に見直すことで、それに向けた努力や成果が適切であるかの確認が可能となり、より現実的で達成可能な目標を設定することにつながるのです。
コーチングによる意識の改革

コーチングは個々人の意識を変革し、自己成長につなげる効果的な手法です。
このプロセスを通じて、個人の潜在能力が引き出され、目標達成に向けた強い動機付けが生まれます。
具体的なスキルの向上だけでなく、意識や価値観の変化も促されるため、プライベートだけでなく、職場でもその効果は大きな影響を与えるでしょう。
主体性を養成するトレーニング
主体性を養成するトレーニングは自己決定能力の向上に重点を置き、個人が自らの責任のもと意思決定を行なう力を育てます。
コーチングでは、目標設定から実行計画の策定、振り返りまでをサポートし、自己主導の学びの環境を提供します。
困難に直面した際にも自ら解決策を見つける能力が身につくため、結果として持続可能な成長を実現することができます。
他人の意見に左右されないための自主性育成
個人が自主性を持って行動するには、他人の意見に流されず、自分の価値観を持ちながら判断できる力が必要です。
コーチングでは、自己認識を深め、内面から湧き上がる声に耳を傾ける訓練を行います。
その過程で、自信の構築と自己肯定感の向上にも繋がり、他人への依存から脱却し主体的な生き方を手に入れることが可能になります。
メンターやロールモデルの活用
メンターやロールモデルを上手に活用することで、目標達成に向けた行動の指針を得ることができます。
模範となる存在から学び、自身の考えや行動を見直す機会を持つことで、より効果的に自己成長を促進させることが可能です。
イメージトレーニングを行いながら、メンターの経験や知識を取り入れ、自己のスキルアップにつなげるのです。
組織による支援体制の構築
組織が持続的な成長を遂げるためには、従業員の潜在能力を引き出し、育成することが欠かせません。
そのためには、適切な支援体制の構築が必要となるでしょう。
資源の配分、環境整備、教育研修への投資が、組織全体の競争力を高めるカギとなります。
環境整備と資源の提供
従業員が能力を最大限に発揮するためには、効果的な環境整備と資源の提供が必要です。
- 作業空間の改善
- 技術ツールの充実
- 適切な情報アクセス
組織としてこれらの条件を整え、従業員が自身の職務に集中しやすい環境を創出することが大切です。
教育研修プログラムの実施
従業員のスキルアップとキャリアの発展を支援するために、教育研修プログラムは重要な役割を果たします。
- オンボーディング研修
- リーダーシップ研修
- 専門技能の向上を目的としたプログラム
学習の機会を増やし、それぞれの従業員が個々の個性と才能を活かせるようなサポート体制が組織全体の成長に直結します。
どうしても納得できない時は
上記を読んでもなお、いい人だけど仕事ができない人が許せない場合は、一度第三者に聞いてもらうとスッキリすることがあります。
電話占いでは、自宅から電話で数分相談するだけで、自分の考え方が変わります。
自分が許せなかった人への対応が変わることで、仕事ができるようになることも。

私も始めは怪しいと思っていましたが、びっくりするほど当たるし、具体的なアドバイスがもらえて気持ちが楽になりました。
悩めるあなたにおすすめサービスはこちら
| こんな人におすすめ | 相談所を比較して選びたい人 結婚を真剣に考えている人 無料で情報収集したい人 | オンラインで婚活したい人 信頼性ある出会いを求める人 忙しくて効率重視の人 | 恋愛や結婚の悩みを相談したい人 婚活の不安を解消したい人 相性や運勢を知りたい人 |
| ⬇︎⬇︎⬇︎ | ⬇︎⬇︎⬇︎ | ⬇︎⬇︎⬇︎ | |
| おすすめ |  結婚相談所比較ネット |  ブライダルネット |  ココナラ占い |
| 料金 | 完全無料 複数の結婚相談所パンフレットを一括請求可能 | トライアルプラン 0円〜 | 1分100円〜 (初回最大30分無料) |
| おすすめ ポイント | カンタン90秒 複数社の資料をまとめて請求 プロの婚活コンシェルジュのサポート付き(紹介・お断り代行・交際サポートなど) | ・結婚に本気な人が98% ・結婚相談所とアプリのいいとこ取り | ・恋愛の悩み相談ができる ・人生や仕事も悩みもOK ・誰にも言えないモヤモヤを解消 ・顧客満足度98% |
| 特徴 | ・厳選大手19社と提携 ・デジタルパンフレットで即閲覧 ・東証プライム上場企業 ・13万人以上の利用実績 ・サービス開始18周年 ・年齢・地域・ニーズに応じた相談所を自動で絞り込み | 結婚相談所のプロカウンセラーのサポート付き 1年以内に結婚したい人向け | 会員登録は無料 ココナラが運営 最大30分無料 |
| おすすめ度 | (5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4 / 5.0) |
| 主な対象年代 | 20代~60代 | 20代〜40代 | 10〜70代 |
| 公式サイト | 詳細を見る https://www.bridalnet.co.jp/ | 詳細を見る https://www.bridalnet.co.jp/ | 詳細を見る https://coconala.com/ |
こちらの記事では、電話占いの活用方法や利用時の注意点などをまとめています。
なお電話占いには、
- どんな人にもおすすめの大手サービス「ココナラ」
- 初回3,000円無料付きの「ウィル」
など、種類別に様々なものがあります。
電話占いって実際どう?【利用手順・おすすめ・メリット・注意点・活用法まとめ】

いい人だけど仕事ができない人についてのよくある質問
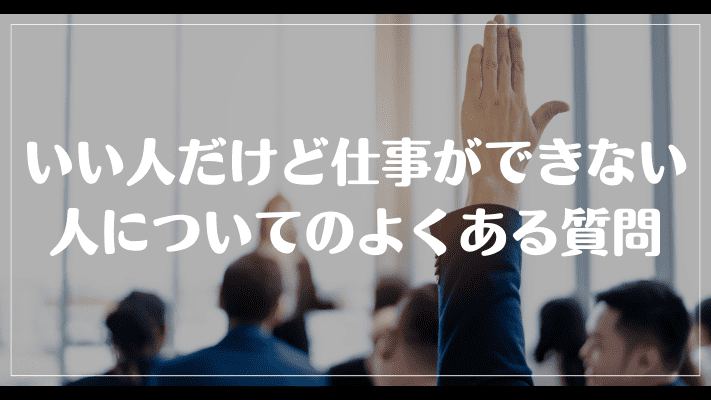

誠実で人当たりも良いが、仕事のパフォーマンスが伴わない人々に関する質問は職場においてよく耳にします。
彼らの特徴、対応策、改善方法などを理解することは、チーム全体の効率と雰囲気を良好に保つために重要です。
仕事ができない人の見分け方は?
仕事ができない人を識別するには、いくつかの兆候に注意を払う必要があります。
- 納期の遅れ
- ミスが多い
- 指示が必要な場面が多い
- 同じミスを繰り返す
- 積極性の欠如
また、このような人は責任を回避する傾向があり、彼らの仕事の結果がプロジェクト全体にどのような影響を及ぼすかに関心を持たないことが多いでしょう。
仕事ができない人との接し方は?
仕事ができない人との接し方は、状況を改善するための重要なステップです。
- 率直かつ建設的なフィードバックを提供し、具体的な目標を設定し、実際の進捗を定期的に確認する
- 彼らの長所を認識し、それを活かせるタスクを割り当て、達成感を感じられるように支援する
- 他のチームメンバーとのコミュニケーションや協力を促進する
- 必要ならば追加の研修を提供して、自信とスキルを向上させる
使えない社員の特徴は?
使えないと評される社員にはいくつかの共通した特性が見られます。
- 主体性を欠き、新しいスキルを学ぶ意欲が低い
- 指示に対して受動的な態度をとり、自ら解決策を見出すことが少ない
- 仕事への熱意やモチベーションが不足
- プロフェッショナルとして成長するための努力を怠る
仕事ができない人はどうすればよい?
個人は自身の弱点を認識し、それに対処するための具体的なアクションプランを策定すべきです。
例えば、仕事のスキルを向上させるために研修やセミナーに参加し、メンターや同僚から積極的にフィードバックを求めることが挙げられます。
時間管理や優先順位付けなどの基本的な職務スキルの習得も、業務効率の向上につながります。
上司やコーチとの定期的なミーティングを設け、進捗を報告することも効果的です。
仕事ができない人の顔つきは?
仕事ができるかどうかを顔つきから判断することは困難であり、それはしばしば誤解を生む可能性があります。
一部の人々は仕事に自信がなかったり途方に暮れたりしている際に特定の表情を見せる場合があります。
困惑、不安、焦りの表情や避ける目線、頻繁なため息などが見受けられることがあり、これらは彼らが仕事上で何らかの困難に直面している可能性を示唆するかもしれません。
一生懸命だけど仕事ができない人は?

一生懸命だけど仕事ができない人は、熱心さとは裏腹に成果が伴いません。
彼らは努力を惜しまないものの、効率の悪い作業方法や不適切なタスク管理によって時間を浪費していることがあります。
また、自らのアプローチを見直す機会が少なかったり、適切なフィードバックが提供されなかったりするため、同じ間違いを繰り返す傾向にあるかもしれません。
仕事ができない人の口癖は?
仕事ができない人の口癖には、「できない」「難しい」「無理」といった否定的な言葉が多く含まれることがあります。
これらの言葉は彼らの自己制限の態度を反映しており、新しい課題に取り組む意欲の乏しさを示している場合があります。
また、「忙しすぎる」「時間がない」という言葉を使うことで、時間管理の問題や優先順位付け能力の不足を表しているかもしれません。
まとめ:いい人だけど仕事ができない人を活かしつつ仕事もできる人材へ

本記事では、一見良い人だが仕事のできない人の特徴とその対処法について詳しく解説しました。
円滑なコミュニケーション能力や誠実さはあっても、業務における具体的な成果が伴わない場合、目標設定と期限の明確化が有効です。
タイムマネジメントを改善し、決断力を培うことは、個人のスキルアップにも繋がります。
フィードバックを活用して自己成長を促し、組織全体でサポート体制を整えることで、その人の強みを最大限に発揮できる場を提供することが大切です。
個々の特性を生かしつつ改善点に取り組むことが、プロフェッショナルへの成長には欠かせません。

職場での人材育成は、一人ひとりに合った方法で行うことが肝要であり、それにより仕事でも人間関係でも充実感を覚えることが可能となります。
また、今後どうすべきかどうか悩んでいる人は、プロの占い師に相談することをおすすめします。
悩めるあなたにおすすめサービスはこちら
| こんな人におすすめ | 相談所を比較して選びたい人 結婚を真剣に考えている人 無料で情報収集したい人 | オンラインで婚活したい人 信頼性ある出会いを求める人 忙しくて効率重視の人 | 恋愛や結婚の悩みを相談したい人 婚活の不安を解消したい人 相性や運勢を知りたい人 |
| ⬇︎⬇︎⬇︎ | ⬇︎⬇︎⬇︎ | ⬇︎⬇︎⬇︎ | |
| おすすめ |  結婚相談所比較ネット |  ブライダルネット |  ココナラ占い |
| 料金 | 完全無料 複数の結婚相談所パンフレットを一括請求可能 | トライアルプラン 0円〜 | 1分100円〜 (初回最大30分無料) |
| おすすめ ポイント | カンタン90秒 複数社の資料をまとめて請求 プロの婚活コンシェルジュのサポート付き(紹介・お断り代行・交際サポートなど) | ・結婚に本気な人が98% ・結婚相談所とアプリのいいとこ取り | ・恋愛の悩み相談ができる ・人生や仕事も悩みもOK ・誰にも言えないモヤモヤを解消 ・顧客満足度98% |
| 特徴 | ・厳選大手19社と提携 ・デジタルパンフレットで即閲覧 ・東証プライム上場企業 ・13万人以上の利用実績 ・サービス開始18周年 ・年齢・地域・ニーズに応じた相談所を自動で絞り込み | 結婚相談所のプロカウンセラーのサポート付き 1年以内に結婚したい人向け | 会員登録は無料 ココナラが運営 最大30分無料 |
| おすすめ度 | (5 / 5.0) | (4.5 / 5.0) | (4 / 5.0) |
| 主な対象年代 | 20代~60代 | 20代〜40代 | 10〜70代 |
| 公式サイト | 詳細を見る https://www.bridalnet.co.jp/ | 詳細を見る https://www.bridalnet.co.jp/ | 詳細を見る https://coconala.com/ |
こちらの記事では、電話占いの活用方法や利用時の注意点などをまとめています。
なお電話占いには、
- どんな人にもおすすめの大手サービス「ココナラ」
- 初回3,000円無料付きの「ウィル」
など、種類別に様々なものがあります。
電話占いって実際どう?【利用手順・おすすめ・メリット・注意点・活用法まとめ】